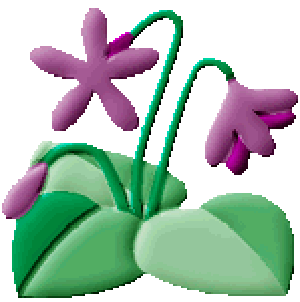
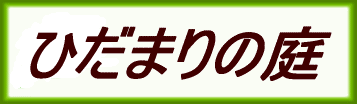
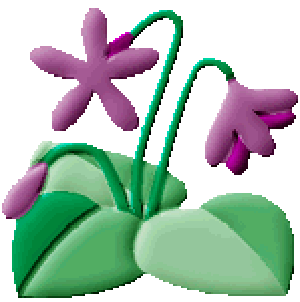
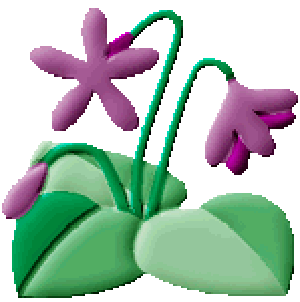
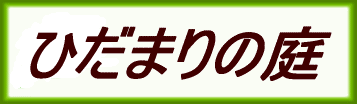
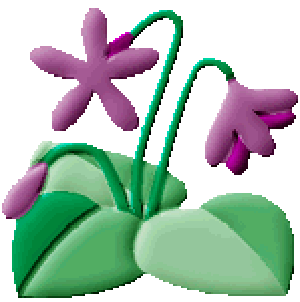
摂 食
【摂食障害】
すみれは生まれたときから口からの摂食(食事)ができません。人間が口から食物を取り込み、噛み砕き、飲み込み、胃に送りこむ『嚥下』という動作は、頭部から首にかけての様々な筋肉や神経の働きにより行われています。すみれはこの一連の動作がスムーズにできません。また、口の周り、口の中が非常に敏感であること、胃食道逆流症(胃の中身が食道へ逆らって流れる)であることも摂食を妨げる原因の一つと言われています。
【現在のすみれの食事】(1歳0ヶ月)
生後2日から、鼻から胃にチューブを通してミルクや、栄養剤を注入しています。現在は1回140㏄のミルクを1日5回与えています。また、嘔吐防止のため、3月上旬に『ハーモニック』という胃の中で固まる経腸栄養剤を使用しましたが、すみれの場合便秘をするため、経過観察中です。
 |
 |
 |
 |
| チューブは1週間毎に取り替えます。 | 大きなシリンジは胃残検査、小さなシリンジは注入後にチューブを白湯で掃除するために使います。 | シリンジを鼻のチューブに差し込み引きます。 胃残の量により注入量を調節し、一緒に引けてくる空気を充分に引いて嘔吐防止をします。 |
我が家ではガラスの容器ににミルクや栄養剤を入れて鼻のチューブにつなぎ、注入を開始します。 |
【摂食訓練】
生後4ヶ月から刺激の少ないシリコンゴム製のスプーンを使い、母乳や果汁を飲み込ませる訓練を行っていました。退院後は、寮育センターで行う月2回のST(言語聴覚療法士)による訓練と、自宅で私が1日1~2回訓練を行っています。、ミルクや果汁などの液体状、5~6口から始まり、前進と後退を繰り返しました。現在ムース状を10口程ゆっくりモグモグと口を動かして食べます。ちなみに1歳現在、歯は生え始めてはいません。
【私が思う〝食べる〟ということ】
最近摂食訓練は泣かせず、無理に口に入れず、〝すみれの笑顔〟を〝ものさし〟にして行うことにしました。少ししか食べられなくても笑いながら食べてくれれば「それでよし」にしました。
人は食べなければ死んでしまいます。食べることは生きること。そんな大事な食事を誰でも苦しみながら毎日続けたくはありません。
「おいしい、楽しい」と感じながら食べることで、会話や笑い、幸せが生まれると思うのです。すみれには何とかして〝食事の楽しみ〟を教えてあげたいと日々努力しています。
 |
| すみれのペースが分からずに、泣いて訓練を拒絶された時期もありました。 口の周りのマッサージ、スプーンを少しずつ口に付けるなど、やりすぎるくらいゆっくりのペースで行うようにしました。 拒絶から1ヶ月半後、こんな笑顔を見せてくれるようになりました。 でもこの笑顔も10口くらいまでの間限定なのです。 |
【現在の摂食訓練用の食事】数種の食材をミキサーにかけ、ムース状にし、なるべく空気を抜いて与えています。わずかでも栄養価が高く、素材の味を楽しめる食材を組み合わせています。{ジャガイモ、ニンジン、牛乳}{カボチャ、鶏のささみ、豆乳}{グリンピース、米かゆ}{イチゴ、豆腐}など、私もどんな味になるかを楽しみながら作っています。できるだけ手作りにこだわっていますが。時間がない時には市販のベビーフードも使っています。
 |
 |
 |
 |
| 好物なのはジャガイモ、ニンジン、牛乳の組み合わせ。 | ジャガイモ、ニンジン、牛乳ミキサーのできあがり図。 芋類、豆類は自然なトロミが付くのでよく使います。 |
豆腐はイチゴや柑橘類の酸味を和らげ、自然な甘みを出します。 すみれは今のところ酸味が苦手ですが他の食材と組み合わせれば食べます。 |
お湯をかけて混ぜるだけのドライフードのパンがゆ。 少量しか食べないので、保存がきくドライフードは重宝します。 |
【食物アレルギー】(1歳1ヶ月)
すみれは、9ヶ月の時に食物アレルギーの検査をしました。結果は異常なし。安心していろんな食物を与えていました。
しかし4月12日午後、突然顔と体中に「じんま疹」が出ました。病院での検査の結果、原因は食物中のタンパク質が引き起こす食物アレルギーでした。午前中に与えたプリンの卵が原因物質となったのです。
食物アレルギーは、じんま疹の他、下痢、呼吸困難、ぜんそくといった症状が一般的で、ひどい場合は死に至ることもあるそうです。怖いですね。
すみれの場合は、じんま疹と軽い気管支炎を起こしました。投薬により一日で改善しましたが、再発防止に、一週間投薬を続けました。
ミルク以外の食物をあまり口にしない頃は、抗体(一定の食物を異物と認定して攻撃してしまう物質)が作られておらず、反応しませんでした。
子供は消化機能が弱いので、大人が食べるものを口にするようになるとタンパク質を消化しきれず、アレルギーの原因物質になることが多いのだそうです。成長し、消化機能が発達すれば、自然と治るケースもあるそうです。
すみれはしばらくの間、卵、鶏肉を食べることができなくなってしまいました。食べることの大切さを唱えていましたが、害になることもあることを身をもって知ったのでした。
【現在の摂食状況】(1歳2ヶ月)
食物アレルギー発症後、一週間は摂食訓練をお休みしていました。そのため食べ物が口に入る感覚を忘れてしまったのか、1~2カ月前ほど楽しそうに食べなくなりました。
量もスプーン10口から5口にペースダウンです。メニューはおかゆミキサー、バナナヨーグルト、ジャガイモと牛乳のミキサー等です。
様子を見ながら新たなメニューを考案し、与えていくつもりです。
食べ物には興味を持っていないようですが、人の食事の様子に興味を持っているようです。
食事中にすみれを食卓に座らせると、私達の食べる様子をジーッと見ていたり、食器に手を伸ばしたりします。
直径10cmの鉢を自分の胸元まで引き寄せて、持ち上げようとして中身の豆腐を床にぶちまけたこともあります。この時にはすみれの行動と、握力の強さに驚きました。
写真は私がパンを食べている様子に興味を示したので、試しにパンを手渡したら10秒間くらいニギニギしてポイしてしまいました。ガラガラなどのおもちゃを手にする時のように自分の口元に近付ける事はしません。
子供は遊びながら食べる事を覚えていくと言いますが、今のすみれにとって食べ物はおもちゃにもならないのかもしれません。
ミルクの量は3月から変わらず140㏄を1日5回。お茶、白湯、イオン飲料を50~100㏄。体重6,8kg。ハーモニックは完全にやめました。体重に対してのミルク量が少ないためか、嘔吐は治まっています。
[5/22更新]
【講演会での話】
5/21、日本栄養士会福祉部が主催した講演会に行ってきました。テーマは「ソフト食」。講師は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の歯科医師です。
「ソフト食」とは食品に手を加えて舌で押しつぶせる程度の柔らかさにし、食欲をそそるように形成した介護食です。ミキサー食や刻み食に代わり、福祉施設などに広まりつつあります。
今回、対象が高齢者であり、具体的な資料も得られなかったので、詳しい内容についての掲載はまたの機会にします。
しかしながら、私が思わずうなずいてしまうような話を講師がされていました。
それは「摂食、嚥下をするためのプロセスの中で、まず人間が行うことは食物を認識し、そしておいしそうだと思い食欲をそそられることである。それがなければ人間の体は消化をするための唾液の分泌などの準備ができず、食物を受け入れづらくなる。」ということでした。
その他にも「舌が働けば、嚥下は可能。そのための舌のマッサージが必要。」「顎をあげた状態で食事を与えてはいけない」といった話もありました。
今回の講演は、今のすみれの摂食訓練に直接は結びつきませんが、参考にはなりました。
今後も、摂食嚥下に関する講演会や、勉強会に参加し、得られた情報は掲載していきます。
[5/27更新]
【摂食訓練食メニュー】
今回は、家族用の食事を作りながら簡単にできる訓練食を考えてみました。
《訓練食アボカドのムースと白身魚のアボカドソースがけ》
① アボカド1/2個を裏ごしし、暖めた豆乳とミキサーにかけます。
そこから適量除き、訓練食とします。残りに塩コショウし、軽くミキサーで混ぜます。
② 白身魚の切り身に酒塩コショウで調味し、1枚ずつ皿に乗せ500wの電子レンジで2分弱加熱します。
③ スライスしたニンニク1/2かけ分を少量のオリーブオイルで香りが出るまで熱します。
④ 加熱した白身魚に③と①の調味したソースをかけます。


《訓練食トマトゼリートとマトのパスタ》
① 大きな鍋に湯を沸かします。
② 小さな鍋に①から湯を大さじ2.5ほど取り、1.5gくらいのゼラチンを加えてふやかし、赤ちゃん用のコンソメを少量加えます。
③ トマト3個を①で湯むきし、種を取りのぞき、ミキサーにかけます。
そこから大さじ2を沸騰させて一呼吸させた②に加え、手早くかき混ぜ、あら熱が取れたところで容器に移し冷蔵庫で冷やし固め、訓練食とします。
残りに塩コショウし、オリーブオイルを少量加えミキサーで混ぜます。
④ ①に多めの塩を加えてパスタを茹でます。
引き上げる3~4分前に1.5㎝長さに切ったアスパラと子房に分けたブロッコリーを茹でます。
⑤ ④が茹で上がったらざるにとって良く水気を取り、ボールに移します。
(※ここで水にさらして冷製パスタにしてもいいです。その場合はパスタを柔らかめに茹でてください)
⑥ ⑤に③のトマトソースと角切りにした、モッツアレラチーズを加え、塩コショウで味を調えて皿に盛ります。
※優しいトマト味のパスタです。

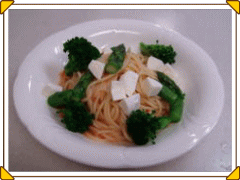
《訓練食簡単ごまプリンとごまと牛乳のプリン》
① 牛乳200㏄に大さじ1の練りごまを加えミキサーにかけます。
そこから50㏄別鍋に移し、小さじ1/2の片栗粉を加え、良くかき混ぜ、火にかけ、固めて訓練食とします。
② 残りに大さじ1の練りごまと、コーヒー用のミルク30㏄、、砂糖10gを加えミキサーで混ぜます。
③ ②を鍋に移し火にかけ、暖まったら、熱湯でふやかした2gのゼラチンを加えよく混ぜ、あら熱を取り容器に移し冷蔵庫で冷やし固めます。
※コーヒー用のパックのミルクは日持ちがするので卵料理や、パスタ、ポテトサラダなど、生クリームの代わりに使っています。
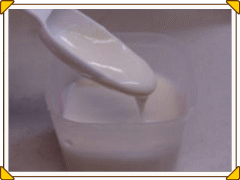
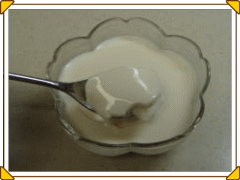
※分量はいずれも約50gの訓練食と大人2人分の材料です。
※大豆類、ゼラチン、ごまなどの種実類でアレルギー反応が出るお子さんもいます。心配な場合は医師に相談してからお使い下さい。
[6/2更新]
【歯医者さんの摂食指導】(その1)
摂食訓練はSTさんだけでなく、種々の専門家の立場からの指導が必要ではないかと私は考えています。
以前、先輩パパママから「神奈川県平塚市の芳賀デンタルクリニック(JR平塚駅から徒歩3分、院長芳賀定先生)で受診したら子供の摂食障害が改善された」との話を聞き、私達も5/30に芳賀先生の摂食指導を受けてきました。
芳賀先生はこれまでにも多くの障害者の診察や摂食指導をされており、CdLSの症例も多く見ておられます。
昨年のCdLSファミリーの集いでも「食べる力を育てるためには」という講演をされています。
初日の今回は、1時間近く時間を取っていただき、すみれの出生時から今日までの状況、摂食状況を説明し、口腔内の診察後、すみれに適した指導をしてくださいました。指導内容は次のとおりです。
○ CdLSの場合、本人の意志を無視して無理に訓練を行うと、数年、口を開けなくなる場合もあるので、絶対に無理してはいけない。
○ CdLS児にとって「1日は48時間位の感覚である」というくらいの認識をもち、とにかくゆっくりと子供のペースに合わせて行う。
○ 自然に食べ物を受け入れさせるには、
① 全身を使って子供が楽しめる運動(高い高いや、ゆりかご遊びなど)をしながら
ア 感覚を育てる。
イ 全身の筋力を育てる。
ウ 空腹を育てる。
② 口や顔を温かいタオルで周りからゆっくりと拭く。
③ 親の小指を口の中に入れ、歯肉を前から後ろに向かってマッサージする。
これらのことを家で実践し、次回は1ヶ月後に診察、指導を受けます。
※先生の許可を受け、掲載しています。


[6/13更新]
【現在の摂食状況】(1歳3ヶ月)
6月12日、歯科医から指導を受けた歯肉マッサージ開始から2週間経ちました。
1~2分くらいなら口に指を入れてもおとなしくしています。摂食訓練食を食べさせる時は、手におもちゃを持たせて私の指を口に入れながらスプーンを入れるとすんなり口を開くようになりました。(写真 左)
機嫌の良いときならスプーン20口食べます。
マッサージを始めてから機嫌の良い時が増えてきています。
今後、島田療育センターと芳賀クリニックさんとの連携で摂食指導をしていただくことになりそうです。


訓練食を作る時、魚や肉も食べさせるためにミキサーよりも粉砕力のあるミルサーを使うことにしました。(写真 右)
タラやサケの切り身を蒸した物をだし汁とミルサーにかけ緩いペースト状にしておかゆに混ぜてます。
余った魚はジャガイモに混ぜてコロッケにしたり、小麦粉と混ぜて薩摩揚げを作ったりしています。

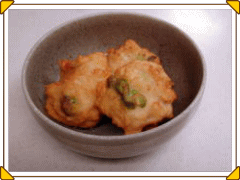
[7/10更新]
【現在の摂食状況】(1歳4ヶ月)
摂食は1日2回、おかゆ、魚、野菜、果物のミキサー食、ヨーグルトをスプーンで10~20口食べています。
療育センターのSTさんから食べる時に舌を出さないようにと指導を受けました。芳賀クリニックには7/29に2回目の摂食指導を受けに行きます。
注入はミルクを140㏄×5回~160㏄×5回に移行中です。
1度に量を切り替えて嘔吐がひどくなった経緯があることから慎重に移行しています。
嘔吐はチューブの交換時くらいです。。
ゲップをする様子を頻繁に見るようになり、笑いすぎ泣きすぎで空気が溜まると嘔吐するということは少なくなりました。
たまに嘔吐したとしても少量です。
[7/31更新]
【歯医者さんの摂食指導】(その2)
7/29、平塚の芳賀デンタルクリニックで2回目の摂食指導と診察を受けてきました。
この日はあらかじめ私が記入した摂食に関するアンケートの項目に沿ってお話が進められました。そして現在の摂食状況と、味わい楽しみながら摂食できるようになって欲しいという私の希望を理解していただきました。
また私が自宅で行っているスタイルでの摂食訓練を見ていただき下記の指導を受けました。
○ 訓練前に頬を指でツンツンと触る事や口の中のマッサージ、訓練後に温タオルで口を押さえるようにして拭き取ること等を続ける。
○ 食間時、頬に5秒以上親の両手を当てる。(写真A)
○ 場所、時間に関わらず、すみれの機嫌が良いときや親が共に行動していて喉が渇いた時など、飲み物、食べ物を指先や綿棒、ストローなどで口唇の間に触れさせる。
自発的に舌を伸ばし舐めさせることで味を覚えさせ興味を持たせる。(写真B)
○ 現在行っている素材の味重視の訓練食だけではなく、濃い味の食物も与えて様々な味を覚えさせるようにする。
みそ汁や煮魚など、すみれの表情を指標にして味を調節する。
○ CdLS児は褒められると伸びる可能性が高いので、訓練中はよく褒めてやる。
歯の生え方を診てもらいました。(写真C)
受け口気味だが奥歯が生えてくれば自然に治るでしょうとのことでした。



[9/13更新]
【現在の摂食状況】(1歳6ヶ月)
摂食訓練は、1日に1~2回、親の食事に合わせて行っています。
おかゆ、魚、芋の煮物、果肉をミルサーにかけた物や、みそ汁、果汁等の水分を与えています。機嫌の良いときは専用スプーンで10~15口食べますが、機嫌が悪いと全く口をあけず、少し無理をして与えようとすると跳び上がって拒否し、むせてしまいます。
しかし、日常の生活の中で、口を開けたり舌をペロペロと出す仕草、舌でおもちゃや身の回りの物を舐める仕草をしていることが増えました。
下の写真は、最近よく食べさせている訓練食とそれを応用して大人のメニューにしたものです。CdLSのお友達の蓮君のHPのリンク先からヒントをもらってモロヘイヤを使ってみました。
モロヘイヤは栄養価が高くて味にクセがなく、刻むとヌメリが出るため、調理すると良い訓練食になりました。調理は簡単。モロヘイヤの葉を茹でて薄めためんつゆやコンソメスープと一緒にミルサーにかけるだけです(写真左下)。
大人のメニューは、これにさらにめんつゆを加え、そばやそうめんの付け汁にしたり、コンソメの方はニンニクを加え温かいスープにします。右下の写真はそうめんとめんつゆで割ったモロヘイヤの上に炒めたなすとベーコンを加えて冷製パスタ風にしたものです。


【歯医者さんの摂食訓練】(その3)
9/12、芳賀デンタルクリニックでの摂食訓練を受けてきました。
最近のすみれの摂食状況を説明し、実際に先生の前で摂食させたところ、それに対して次の指導を受けました。
○ 口の中のマッサージ(ガムラビング)を、もう少し長く丁寧に行い、食べ物が口の中を流れる感覚を教える。
(食べ物は前から後ろに流れていくので、口の中で一定の流れの感覚を覚えさせるために、前歯から奥歯へ10ストローク、テンポ良く指を動かす。)
○ 摂食状況が一進一退しても、根気よく同じ事を半年くらいかけて行い、よく観察する。
出来るようになったら次のステップに半年単位で取り組む。決して焦ってはいけない。
[12/21更新]
【現在の摂食状況】(1歳9ヶ月)
9月13日の指導から3ヶ月、体調不良のため芳賀クリニックの指導は2回続けてキャンセルすることになってしまいました。回復を待って11月以降から前回の指導を踏まえて家での訓練を再開しました。
スプーンよりも指で与えた方が受け入れやすい様子だったので、軽く歯の表面をマッサージし、口を開けたところでミキサー食を押し込んだりしていました。1回の量は、今までと変わりません。
棒付きのキャンデーを与えたところ、手で抵抗しながらも舌を出してペロペロとなめました。他にも味の濃い目の煮物のミキサー食を与えていました。薄味よりも濃い味の方が食べっぷりが良いです。
【歯医者さんの摂食訓練】(その4)
12月16日、芳賀クリニックへ行きました。
3ヶ月間の摂食状況を説明しながら摂食の様子を見てもらい、先生から次の点について指導を受けました。
○ 食べ物を目の前にちらつかせて「これから訓練するんだ」という印象を与えると緊張しやすいので、おもちゃでなど気をそらせながら与える。(左下の写真は遊びながらキャンデーを舐めているところです。)
○ 今までガムラビング(口中マッサージ)は、ジュースなどを使って行っていたが、濃い味の食事や菓子類の場合、味に慣れさせたり受け入れやすいという点では有効であるが虫歯になりやすいので、今後は緑茶などを使って行う。
○ 歯磨きはこれまでのガーゼ磨きを卒業し、そろそろ歯ブラシをきちんと使い始めること。歯ブラシは歯に当てて小刻みに震わせるて行う。(写真右下は、先生の実演)内側は舌で自然に洗浄されるので磨かなくても良い。細菌は寝ている間に一番増殖するので、寝る前と朝に行う。
また最近、咳き込んで嘔吐することが頻繁であることを話しました。
先生によると、濃い味の刺激やマッサージの効果により唾液腺の働きが活発になり、大量の唾液が出始めているはず。すみれはそれを処理仕切れずに口の中に溜まり、むせているのかもしれない。胃食道逆流症の症状である可能性も否定できない、とのことでした。
それを受け、胃食道逆流症(胃の中身が食道へ逆らって流れる)の検査を一月以降に受けることを検討しています。


【現在の摂食状況】(2歳0ヶ月)
鼻のチューブがとれた事で嚥下(飲み込むこと)はしやすくなったようです。飲み込んだ後に見せる笑顔が多いし、舌で味わうような仕草も見せます。
しかし口の中と周囲の敏感さはとれず、スプーンを拒否しています。仕方がないので私の指でおかゆ、カボチャの煮物などミルサー食を1日1~2回あたえています。量にすると小さじ1杯程度です。鼻からのチューブの違和感がなくなれば摂食は進むのではと期待していましたが、まだ時間はかかりそうです。
胃瘻からは、フォローアップミルクと新生児用のミルクを混合して160ml×5回、1日5~10gの5倍粥のミルサー食を注入しています。(写真)
入院中の経管栄養剤が合わなかったことと、一般の様々な食品から自然な栄養摂取をさせたいという私の希望から、退院1ヶ月後の診察まで離乳食を試すことにしたのです。
離乳食を入れるに当たって指標の数字が欲しいと思いました。しかしすみれは健常児と違い2歳児でも立ったり歩いたりしないし、身長が低く体重も軽いのでのですみれに見合った必要な栄養量の算出の仕方が分かりませんでした。そこで入院中の先生の話、「すみれ教室」のお友達の話や私の手持ちの資料を参考に自分なりに計算してみました。
現在のすみれの体重は7.6kg、身長71㎝です。
① まず、すみれの身長・体重から乳幼児の発育状況を確かめるのに使われる「カウプ指数」(CdLS児に当てはめていいのかどうか分かりませんが)を計算すると約15で、やせ気味の領域に入ります。(別表参照)
② 1歳までの乳幼児が1日に必要なエネルギー量(エネルギー所要量)は、体重(kg)×100(kcal)で算出します。すみれは2歳ですが発育が遅れているので、この式に当てはめていいようです。
計算上は760kcalですが、すみれはやせ気味であるので高めの800kcalに設定してみました。
③ ②で算出した必要なエネルギー量と、現在すみれが注入している粉ミルク缶に表示してある成分表から実際にミルクから摂取しているエネルギー量を比較してみると、270kcal足りませんでした。
④ そこで不足している270kcalを全てお粥(米)でまかなおうとすると、1日約70g分の米が必要で、5倍粥だと350mlになります。しかし、一日5回の注入に分けたとしても1回の注入で70mlのお粥になってしまい、今のすみれは噴門形成術で胃が小さくなっていることもあり、1回米5~10g分の粥(35~50ml)でも苦しがるような状態で、事実上必要なエネルギー量を十分に摂取することはできません。
⑤ また、エネルギー量以外の栄養素についても計算上必要な量と実際にミルクから与えている量を比較すると、タンパク質、ビタミンD、リン、マンガン、銅が足りないことが分かりました。
このような計算結果から、経口からの栄養摂取が進まなければ胃瘻からの離乳食注入はなかなか困難なようです。
しかし、ミルクの種類や離乳食との量的バランスなどを工夫し、すみれの体調を見ながら来月の診察まで離乳食注入を頑張ってみるつもりです。
《参考》
カウプ指数=体重(㌘)÷身長2(㌢)×10
【現在の摂食状況】(2歳5ヶ月)
手術後、吐き気や嘔吐することが無くなったので、家での摂食訓練を再開しました。
機嫌が良ければ、私達が並んで食事をしている場所に割り込んで入ってきます。お粥のミルサー食、トマトの絞り汁、みそ汁の上澄みなどを指ですくって口に入れると、味わうような仕草も見せます。しかしスプーンでは拒否し、指でも2~3口がいいところです。
平塚の芳賀クリニックには昨年以来ご無沙汰してしまっています。秋以降に診察してもらおうと思ってます。
【現在の摂食状況】 (2歳7ヶ月)
摂食状況は相変わらずです。気まぐれで親の食事中に寄ってきて汁物を舐める程度です。
しかし、最近、歯磨きがしやすくなりました。口を固く閉ざしてしまい、歯ブラシの入る余地が無かったのですが(いつの間にか上下8本ずつ、16本生えました)、歯ブラシを口に入れたときの嘔吐が少なくなり、以前より身をまかせるようになり、奥歯、歯の裏側も磨けるようになりました。敏感さが無くなり、口に物が入ることに抵抗が無くなっていくことに期待したいです。
【歯医者さんの摂食訓練】(その5)(2歳10ヶ月)
1月15日、1年ぶりに平塚の芳賀クリニックに行ってきました。
摂食状況は相変わらずですし、あまりに嫌がるので私も家での訓練をさぼりがちでした。しかし歯がしっかり生えたので虫歯予防のため歯磨きだけは毎日行っていました。これが幾らか良かったのか、診断では口の開け方が良くなっているとのことでした。
今後、以前指導されたホットタオルや口中のマッサージ、歯磨きにより口の周りの敏感を取る習慣を復活させるよう指導されました。また前回、歯の裏側は唾液や舌で洗浄されるので無理に歯磨きはやらなくても良いと言われていました。(すみれはほとんど食べ物を口に入れていないため。)しかし何となく気持ちが悪いので、ついついやってしまっていたのですが、改めて嘔吐を引き起こす原因になるのでやらなくて良いと注意されました。
【現在の摂食状況】 (2歳11ヶ月)
1日1回の歯磨き、1日2回ホットタオルの顔当て、指での口中のマッサージを行っています。しかし、すごく嫌がるので先生の指導を少し変え、時間を短くしたり、マッサージの順番も変えています。
栄養の濃度が上げられないことから消化器官が弱っていることを疑っていましたが、とても活発に動き、元気です。そのため1~2日に1回行っていた家での摂食訓練を2月末頃より1日1~2回に増やしました。
内容はバナナを牛乳でのばしたもの、ココア、果汁のとろみ、野菜の煮物のペースト、みそ汁等をマッサージの後に指で2~3口舐めさせています。
反応はその時々で、抵抗して全く受け付けないこともあれば、笑って舌を出して舐めたりすることもあります。
【現在の摂食状況】 (3歳0ヶ月)
1日1回の歯磨き、2回のホットタオルの顔当て、指での口中マッサージを続けています。
おもちゃ等を舐めてどんな物か確かめていることがあります。最近はビニールのアンパンマンの起き上がりこぼしを舌を出してベロベロ舐めます。。ビニールのツルツルした感触が気持ちいいのかもしれません
摂食も少し前進しました。嫌がっていたスプーンも3~4回、口に入れるようになりました。内容はいちご、パイン、いよかん、バナナ等の果汁のとろみです。いちごは臭いで分かるのか口に付ける前から笑っていました。口に入ると味わうような素振りを見せ、すんなりと飲み込みます。でも今は3~4口で満足なようです。気が向かなくなると、スプーンを近づけただけで手で振り払おうとして嫌がります。
【現在の摂食状況】 (3歳4ヶ月)
約一ヶ月間、家での摂食訓練はお休みしていました。風邪のため咳と鼻水でむせていたためです。7月後半、症状が落ち着いてから再開しました。指でいろんな食材と柔らかさのミルサー食を食べさせています。敏感さは変わりませんが、口に入れてしまうと味わうような仕草を見せたり、良く笑っています。10回くらい口に指を運ばせてくれます。
久々に家族も一緒に食べられるすみれ用のメニューを考えてみました。
《枝豆とポテトのペースト》(晩酌のつまみの残りで)
① 茹でてさやから出した枝豆に、味噌・昆布茶・豆乳・塩を加え、ミルサーやミキサーで粒が無くなるまで粉砕する。
② 裏ごしたポテトに添え、一緒にに食べる。
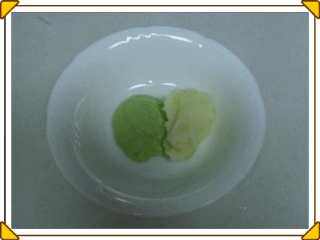
《ラタトウイユのパングラタン》(冷蔵庫の残り野菜で)
① 茄子、きゅうり、ピーマン、キャベツ、玉葱、人参などあり合わせの野菜を適当に切る。
② ①をニンニク、オリーブ油で炒め、ホールトマトを加えてコンソメ、塩コショウで味を調える(家族にはパスタ、豆腐ステーキオムレツなどのソースとして使う)。
③ ②をミルサーにかける。
④ 食パンをちぎって水、又は豆乳や牛乳などと一緒にミルサーにかける。
⑤ ④に③をかけて粉チーズを振り、オーブンで適宜焼く。
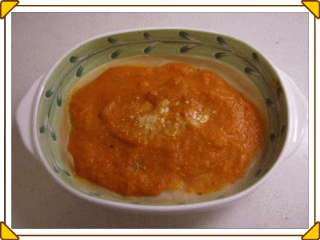
【現在の摂食状況】( 3歳5ヶ月)
体調も機嫌も良く、外からの刺激を抵抗なく受け止めて喜んでいます。以前は過敏のため受け入れられなかったことができるようになり、それを新たな喜びとして感じているようです。そのためか、家での摂食訓練でも機嫌良くしています。
口に入れるまでは以前のように拒否しますが、一度口の中に入ってしまうと飲み込んでから首を横に振って大笑いしています(「イヤイヤ」ではなく、楽しさの表現です)。指でバナナやお粥、親のおかずをミキサーでペースト状にしたもの等を10回程度口に入れます。先日は冷たくて苦手だったアイスクリームも口にできました。しかし、「食べている」と言うより今のすみれの中では楽しい遊びの一つになっているようにも感じ、そのうちこの遊びに飽きがくるかもしれませんが、今のうちに少しでも「食べる」という行為を覚えてくれたらいいです。
これまで口から「少量舐めるだけ」に留まっていましたが、体調が良いので栄養剤の他に摂食訓練の残りを注射器で一日に30~50g程注入し始めました。すみれは栄養剤以外の物を体の許容量以上入れたり、速い速度での注入は下痢を起こします。今回も入れ始めは案の定下痢しましたが、少しずつ慣らせば大丈夫なようです。様子を見ながら「栄養剤以外の食物」に体からも慣らせたいと思っています。